認知行動療法とは
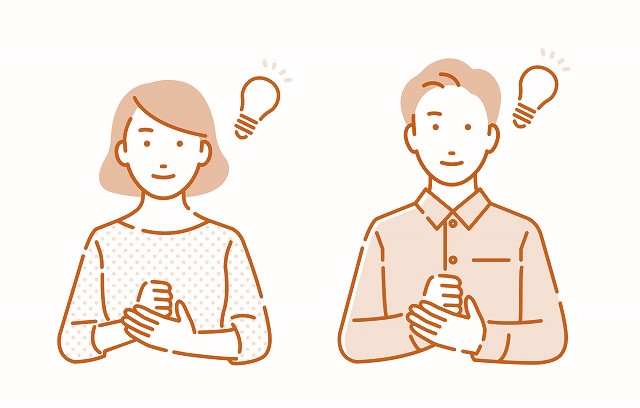 認知行動療法は、「考え方」や「受け取り方」などの「認知」に注目した心理療法です。悩みを抱えると、思考がマイナス方向に偏り、自分を追い詰めてしまうことがあります。偏った思考を客観的に見直し、前向きに進めるよう「考え方の癖」に気づく練習を行います。患者さん自身の気づきを大切にしながら、問題解決に向けた行動を一緒に考えていくのが特徴です。
認知行動療法は、「考え方」や「受け取り方」などの「認知」に注目した心理療法です。悩みを抱えると、思考がマイナス方向に偏り、自分を追い詰めてしまうことがあります。偏った思考を客観的に見直し、前向きに進めるよう「考え方の癖」に気づく練習を行います。患者さん自身の気づきを大切にしながら、問題解決に向けた行動を一緒に考えていくのが特徴です。
認知行動療法における「認知の歪み」とは
 認知の歪みとは、物事の受け取り方や解釈に偏りが生じる心理的な現象を指します。これは認知行動療法において重要な概念で、下記のような特徴があります。
認知の歪みとは、物事の受け取り方や解釈に偏りが生じる心理的な現象を指します。これは認知行動療法において重要な概念で、下記のような特徴があります。
同じ出来事に対して、歪んだ捉え方をすることで、不安やイライラ、ネガティブな感情が生じます。
全ての人に程度の差はありますが存在し、完全に無い人はいません。
近年では「歪み」という表現よりも、個人の「特性」として捉える傾向があります。
代表的な認知の歪み
- 全か無か思考:物事を極端に捉える
- 過度の一般化:一度の出来事を全てに当てはめる
- 心のフィルター:ネガティブな面だけに注目する
- マイナス化思考:良いことも悪く解釈する
- 結論の飛躍:根拠なく悲観的な結論を出す
認知の歪みは、うつ病や不安障害などの精神疾患の発症や維持に関与していると考えられています。認知行動療法では、これらの歪んだ認知パターンを特定し、より適応的な思考へと修正することを目指します。
認知行動療法でとらえる点
ストレスフルな出来事に対する反応を、下記の4つの側面から分析していきます。
- 認知(頭に浮かぶ考え)
- 感情(感じる気持ち)
- 身体(体の反応)
- 行動(振る舞い)
認知行動療法は自分でできる?(セルフケアできる?)
近年、CBTは専門家によるセッションだけでなく、書籍やオンライン講座、スマートフォンアプリなどを通じてセルフヘルプの手段としても広く認知されるようになりました。
注目される理由としては以下が挙げられます。
- 再現性の高さ:CBTの基本技法は体系化されており、個人でも独学で学びやすい構造になっています。
- 即効性と継続性:認知の修正や行動の変化がうまくはまると、短期間で気分の改善を感じられるケースがあります。また、技法を学べば日常的に使えるスキルとして定着しやすいです。
- 科学的根拠(エビデンス)の充実:世界各国で数多くの研究が行われており、CBTが効果的であることが比較的明確に示されています。
ただし、セルフケアだけでは対応が難しい症状もありますので、無理をせず必要に応じて医療機関に相談する姿勢は大切です。
認知行動療法の対象となる
主な病気
- うつ病
- 躁うつ病(双極性障害)
- 統合失調症
- パニック障害
- 強迫性障害(強迫症)
- 社交不安障害(社交不安症)
- PTSD(心的外傷後ストレス障害)
- 摂食障害(過食症・神経性無食欲症)
- 適応障害
- 睡眠障害(不眠症)
など
認知行動療法のメリット
精神疾患の治療と予防
認知行動療法は、うつ病や不安障害、ストレス関連障害など、さまざまな精神疾患の治療に効果があります。また、治療時だけでなく、治療後の精神疾患発症の予防にも繋がります。
日常生活への応用
認知行動療法で身に着けたスキルは、仕事や学校生活など、日常生活のさまざまな場面で活用できます。
長期的な効果
認知行動療法は、治療終了後も学んだスキルを継続できるため、長期的な効果が期待できます。
副作用が少ない
薬物療法と比較して、副作用の心配が少ない点も認知行動療法の特徴です。
思考パターンの改善
ネガティブな自動思考を修正し、より冷静で前向きな思考ができるようになります。
科学的根拠(エビデンス)の充実
世界各国で数多くの研究が行われており、CBTが効果的であることが比較的明確に示されています。
認知行動療法のデメリット
時間がかかる
効果を実感するまでに16週間程度かかります。薬物療法と比較して、即効性に欠ける点がデメリットとなります。
費用面の負担
保険適用にて行える場合もありますが、条件次第で自費診療となることもあります。
自己学習の難しさ
認知行動療法を行う場合、下記のような課題があります。
- 認知の歪みに気づきにくい
- 適切なスキルを身につけるのに時間がかかる
- 途中で中断してしまう可能性がある
認知行動療法の流れ
1問題の整理(問題と目標を明確にする)
 患者さんの抱える悩みや課題を医師とともに整理していきます。
患者さんの抱える悩みや課題を医師とともに整理していきます。
まずは「自分がどのようなことで悩んでいるのか」を整理しましょう。
・最近、仕事や学校に行く前にひどく憂鬱になる
・特定の場面で強い不安を感じる
・人間関係の些細なトラブルで落ち込みが続く
…など、日常生活の中でどのような場面や出来事が気分を大きく左右するかを洗い出します。
次に、どのような変化を望んでいるかという目標も設定しましょう。
たとえば、「朝起きたときに憂鬱感があっても、出勤へのハードルを下げたい」「特定の不安場面でも落ち着いて行動できるようになりたい」など、具体的なゴールを定めると、後のステップで達成度を測りやすくなります。
2思考記録表を活用する
CBTを代表する技法の一つに「思考記録表」があります。
自分の気分が大きく変化した場面や、強い感情が生じた瞬間をきっかけにして、「そのときどのような考え(自動思考)が浮かんだか」を書き出していきます。
以下のような項目を設けるのが一般的です。
- 状況:何が起きたか? どんな場面だったか?
- 気分や身体反応:そのときの感情の種類や強さ(0~100で数値化)
- 自動思考:頭に浮かんだ考えやイメージ(例:「自分はダメだ」「みんな私を嫌っている」など)
- 根拠:その思考を裏付ける事実、反対にそれを否定する事実
- バランスのとれた考え方:もう少し客観的かつ現実的に捉えるとどうなるか?
- 書き換え後の感情変化:気分はどう変わったか?
こうして記録をつけることで、自分の思考パターンのクセに気づきやすくなり、「本当にそうだろうか?」と冷静に再検討するきっかけが得られます。
3認知の歪みを見つける
CBTでは、認知の偏りやネガティブな思考パターンを「認知の歪み」と呼びます。代表的な認知の歪みには以下のようなものがあります。
- 全か無か思考:物事を「完璧にできるか、まったくできないか」の二択で捉える
- 一般化のしすぎ:一度の失敗を「自分はいつも失敗ばかりする」と拡大解釈する
- 自己関連づけ:何か悪いことが起きたとき、根拠なく自分に責任があると考える
- べき思考:「~すべき」「~でなければならない」と考えすぎて自分を追い詰める
思考記録表をつけていると、これらの歪みが頻繁に登場する可能性が高いことに気づくでしょう。
歪みに気づいたら、その思考が「本当に妥当か?」「根拠はあるか?」と問いかけながら、より柔軟で現実に即した考えに書き換える練習をします。
4行動実験・行動活性化を試みる
認知面での書き換えと並行して、行動にもアプローチしてみましょう。
「自分は人に嫌われているから、誘っても誰も来ないはず」という思い込みがある人が、実際に数人に声をかけてみるなど、小さな「行動実験」を行うと、「意外と参加してくれた」など新たな発見が得られます。
また、「気分が落ち込んでいるから何もできない」と感じている場合でも、あえて楽しめそうなことや少しの家事などを短時間やってみて、「意外とできた」「少し気分が上がった」などの成功体験を積み重ねる「行動活性化」も効果的です。
こうした小さな成功が続くと、自分の考え方や行動に対する肯定感が増し、うつや不安の悪循環を断ち切りやすくなります。
5経過を振り返り、スキルを定着させる
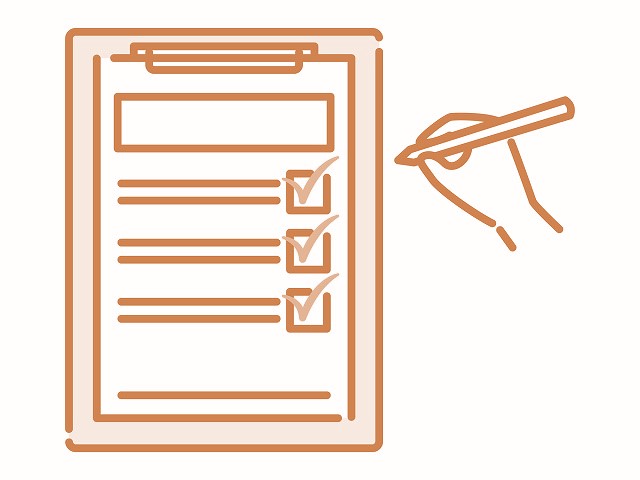 CBTのセルフケアは一度やって終わりではなく、継続と振り返りが大切です。
CBTのセルフケアは一度やって終わりではなく、継続と振り返りが大切です。
1~2週間ごとに自分の思考記録表を振り返り、「どんな場面でどんな思考のクセが強く出たか」「行動実験の結果はどうだったか」を確認します。
その上で「もっとこうしたらよかった」「次は別のやり方を試そう」など、改善点と具体的な方策を考える習慣を続けると、自然にCBTのエッセンスが日常生活に根付いていきます。
セルフCBTを行う際の注意点
自分でできるCBTは、有効なセルフヘルプの方法となり得ますが、次のような場合には注意が必要です。
- 深刻な症状がある場合:自殺念慮が強い、まったく動けないほどの体調不良などの場合は、セルフケアだけでの対処は危険です。すぐに専門医療機関へ相談しましょう。
- 自責感が強まる場合:思考の歪みに気づいたことで、逆に「自分はこんなに歪んだ考え方をしていたんだ」と落ち込みが強くなるケースもあります。あくまで「気づき」は改善への第一歩であり、自分を責める材料にしないことが大切です。
- 完璧主義に陥る場合:「すぐに考え方を正しくしなければ」「うまくいかないのは自分の努力不足だ」など、かえって自分を追い詰めないよう注意しましょう。
- 行動実験の無理な拡大:小さな行動実験で徐々に成功体験を得るのが原則です。いきなり高いハードルを設定して失敗すると逆効果になりかねません。
これらの点を踏まえつつ、セルフケアでの効果が感じられない、むしろ悪化しているように感じる場合は、早めに専門家(精神科医・臨床心理士など)と連携してください。
医療機関や専門家との併用がおすすめ
セルフCBTはあくまで「自助」の手段であり、場合によっては限界があります。
特に、うつ病や不安障害などの診断がある場合は、薬物療法や専門家によるCBTセッションとの併用を考慮するとよいでしょう。
専門家と連携するメリットには以下が挙げられます。
- 客観的な視点で考え方のクセを指摘・修正してもらえる
- セルフケアがうまく進まない時の原因を一緒に探れる
- 薬物療法や他の心理療法との相乗効果が期待できる
- 安心して取り組めるサポート体制が整う
医療機関やカウンセリングルームを探す際は、「認知行動療法を提供している」旨を明記しているところを選ぶとスムーズに相談が進むでしょう。
セルフCBTを継続するコツ
認知行動療法は、「気づき」と「行動」のサイクルを回すことが本質です。セルフケアとしても、同じように継続しながら自己理解を深めていくことで、本来の効果を実感しやすくなります。
以下のコツを参考にしてみてください。
小さな成功を大切にする
少しでもポジティブな変化を感じられたら、それをしっかり認めてあげる。自分を褒める習慣がモチベーション維持につながります。
定期的な振り返りを習慣化
週末や平日の決まった時間に「思考記録表」を見返す、あるいは日記をつけて変化を追う。継続的なチェックで「いつの間にか元の思考パターンに戻っていた」という事態を防ぎます。
仲間やサポートを得る
同じ悩みを持つ人との情報交換や、家族・友人の理解も大きな励みになります。「一人でやらなければ」と抱え込まず、時には周囲を巻き込みましょう。
過度に厳しくならない
セルフCBTは「上手くいかないことがあっても、また修正できる」柔軟性がポイント。完璧を求めすぎると長続きしません。
認知行動療法のよくある質問
認知行動療法は薬物療法と併用できますか?
併用できます。薬物療法と認知行動療法を組み合わせることで、単独で行うよりも効果が大幅に上がることが分かっています。バランス良く組み合わせて、治療効果を最大限高めていきます。
認知行動療法と他の精神療法の違いは何ですか?
認知行動療法の特徴は、下記になります。
- 物事の受け止め方や考え方(認知)に焦点を当てる
- 治療者(専門家)が積極的に質問する
- 日常生活の場面を治療の題材とする
- 患者さんと治療者(専門家)が協力して取り組む



