一般雇用と障害者雇用
一般雇用と障害者雇用(対象者の違い)
 一般就労(一般雇用)では基本的に企業の応募条件さえ満たせば、障害の有無に関係なく誰でも応募できます。一方、障害者雇用(いわゆる障害者枠採用)は応募者に一定の条件があり、原則として身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれかを所持していることが必要です。これは法律上、「障害者」の定義に該当し、企業の法定雇用率の対象となる障害者であることを意味します。具体的には、視覚障害や聴覚障害、肢体不自由などの身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)が該当します。2018年の法改正以前は身体・知的障害のみが対象でしたが、2018年4月から精神障害者(発達障害者を含む)も法定雇用率の対象に加えられました。したがって現在はこれら3種類の手帳を持つ人が障害者枠求人に応募できます。
一般就労(一般雇用)では基本的に企業の応募条件さえ満たせば、障害の有無に関係なく誰でも応募できます。一方、障害者雇用(いわゆる障害者枠採用)は応募者に一定の条件があり、原則として身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれかを所持していることが必要です。これは法律上、「障害者」の定義に該当し、企業の法定雇用率の対象となる障害者であることを意味します。具体的には、視覚障害や聴覚障害、肢体不自由などの身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)が該当します。2018年の法改正以前は身体・知的障害のみが対象でしたが、2018年4月から精神障害者(発達障害者を含む)も法定雇用率の対象に加えられました。したがって現在はこれら3種類の手帳を持つ人が障害者枠求人に応募できます。
ただし手帳を持っている場合でも、障害当事者が希望すれば一般枠で応募すること自体は可能です(企業側は採用時に障害への配慮義務を負いません)。なお、障害者枠で採用された場合は入社時に手帳の提示が求められるため、就職を目指すなら事前に手帳を取得しておく必要があります。
また、「オープン就労」(障害を開示して障害者枠で働く)か「クローズ就労」(障害を開示せず一般枠で働く)かによって、就職後の定着率にも大きな差が出ています。厚生労働省の調査によれば、障害者枠で就職し障害を開示して働いた場合は定着率が高いのに対し、障害を開示せず一般雇用で働いた場合は大幅に低い傾向があります。これは企業側の障害理解や配慮体制の有無が影響していると考えられ、障害者雇用枠では職場に障害への理解があり合理的配慮も受けられるため定着しやすく、一般枠で障害を隠して働くと支援を得られず離職につながりやすいと言えます。
雇用形態の違い
 一般就労では正社員(無期雇用の常勤)から契約社員・派遣社員・パート・アルバイトまで多様な雇用形態があります。企業の求人は正社員募集が多いですが、近年は非正規雇用も増えています。一方、障害者雇用(障害者枠)では、募集ポジションや企業規模にもよりますが、非正規雇用(有期契約やパートタイム)の割合が高い傾向があります。厚生労働省の障害者雇用実態調査では、障害者枠で働く人の中で正社員の割合は身体障害者が比較的高めな一方、知的障害や精神障害者では正社員が少なく、短時間勤務や契約社員が中心です。
一般就労では正社員(無期雇用の常勤)から契約社員・派遣社員・パート・アルバイトまで多様な雇用形態があります。企業の求人は正社員募集が多いですが、近年は非正規雇用も増えています。一方、障害者雇用(障害者枠)では、募集ポジションや企業規模にもよりますが、非正規雇用(有期契約やパートタイム)の割合が高い傾向があります。厚生労働省の障害者雇用実態調査では、障害者枠で働く人の中で正社員の割合は身体障害者が比較的高めな一方、知的障害や精神障害者では正社員が少なく、短時間勤務や契約社員が中心です。
このように障害者枠では有期契約や短時間勤務での採用が多く、正社員登用は少なめなのが現状です。企業によってはまず契約社員や嘱託社員として採用し、働きぶりを見てから正社員登用を検討するケースもあります。
給与や待遇面では、同じ企業・同じ職務であれば障害者だからといって差をつけることは法律上許されません。ただし実態として、障害者枠では職務内容が限定的だったり短時間勤務だったりするため、平均給与水準は一般より低くなりがちです。雇用形態が非正規の場合は賞与や昇給、福利厚生面でも制限があることが多いですが、企業によっては障害者枠でも正社員採用し、健常者と同等の待遇を付与している例もあります。
大企業では親会社が「特例子会社」を設立し、そこで障害のある社員を多数雇用している事例もあります。特例子会社では給与水準や福利厚生が親会社に準じるケースもあり、働きやすい環境が整えられています。
採用プロセスの違い
求人の探し方
一般就労の場合、民間の求人サイトや転職エージェント、企業の採用ページ、ハローワークの一般求人など様々な経路で応募できます。障害者雇用(障害者枠)の場合もハローワークは重要な窓口ですが、各地のハローワークには障害者専門窓口があり、専門の職業相談員が求人を集中的に案内します。さらに障害者向け求人サイトや転職エージェント、就労移行支援事業所の紹介など、障害者に特化した支援サービスが多数存在します。企業によっては自社サイトに障害者採用ページを設け、直接募集している場合もあり、地域によっては障害者向けの合同企業面接会が定期的に開催されることもあります。
選考方法
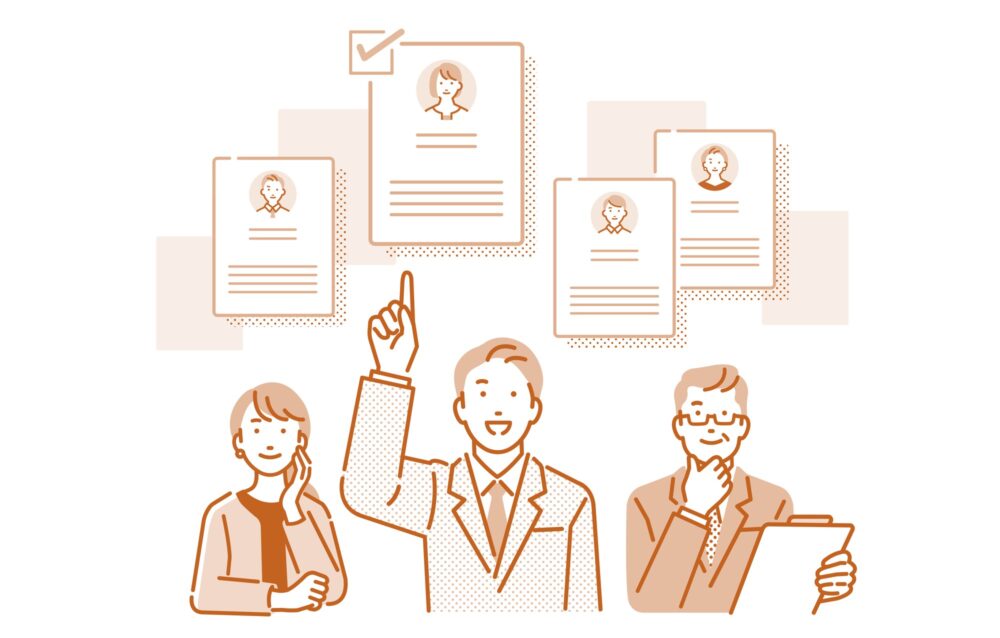 一般枠の採用試験では、書類選考(履歴書・職務経歴書)後に筆記試験(SPIなど)や面接が複数回行われることがあります。障害者枠の場合、基本フローは変わりませんが、筆記試験や適性検査を免除したり、実技試験や職場実習を取り入れて適応度を確認するなど、企業側も配慮を行うケースが多いです。応募書類として、障害者手帳の種類や配慮事項を記入する書類の提出を求められる場合があります。
一般枠の採用試験では、書類選考(履歴書・職務経歴書)後に筆記試験(SPIなど)や面接が複数回行われることがあります。障害者枠の場合、基本フローは変わりませんが、筆記試験や適性検査を免除したり、実技試験や職場実習を取り入れて適応度を確認するなど、企業側も配慮を行うケースが多いです。応募書類として、障害者手帳の種類や配慮事項を記入する書類の提出を求められる場合があります。
面接のポイント
 一般枠では志望動機や経験・スキル、意欲などを中心に問われますが、障害者枠の面接ではこれに加え「障害の内容・症状」「業務上の困難と可能なこと」「必要な配慮」について詳しく尋ねられます。企業は社員が職場で安定して働けるか、どの程度の配慮が必要かを重視しているためです。自分の障害特性と必要なサポートを具体的に伝える準備をしておくことが重要です。
一般枠では志望動機や経験・スキル、意欲などを中心に問われますが、障害者枠の面接ではこれに加え「障害の内容・症状」「業務上の困難と可能なこと」「必要な配慮」について詳しく尋ねられます。企業は社員が職場で安定して働けるか、どの程度の配慮が必要かを重視しているためです。自分の障害特性と必要なサポートを具体的に伝える準備をしておくことが重要です。
働き方の違い
合理的配慮の有無
障害者雇用(障害者枠)では、法律上、企業は障害のある労働者に対して合理的配慮を提供する義務を負います。具体的には、出勤時間を通勤ラッシュを避けた時間帯に調整する、身体障害者向けに執務スペースや設備をバリアフリー化する、精神障害のある方に対しては業務量を調整したり定期的な面談を設けるなどが挙げられます。一般枠の場合、障害が未開示なら配慮を得るのが難しく、結果的に勤続が難しくなるリスクもありますが、障害者枠なら企業側の理解や配慮が期待できます。
業務内容や職種
一般就労では営業、企画、技術、事務など幅広い職種に配属される可能性がありますが、障害者枠の場合は障害特性に応じて内勤事務や軽作業、庶務サポートなど、負担が少なく取り組みやすいポジションが多いです。ただし最近では障害者枠であっても専門職(プログラマー、デザイナーなど)を募集したり、成果次第でリーダーに昇格する例も増え、以前より職種の幅は広がっています。
勤務時間・労働条件
一般就労ではフルタイム(週40時間)や残業、転勤があり得ますが、障害者雇用は短時間勤務や時差通勤など柔軟な働き方を認める例が多く、残業を免除したり通院休暇を設定している企業も多いです。障害者枠では個別の事情に合わせて労働条件を調整しやすい反面、責任あるポジションへの配属や収入アップが限定的になることもあります。
支援制度の違い
企業への助成・支援
障害者雇用を推進するため、企業向けに国や自治体から様々な助成金・支援策が用意されています。例えば特定求職者雇用開発助成金やトライアル雇用助成金、職場のバリアフリー化にかかる費用を一部補助する制度などがあり、法定雇用率を満たす・超える企業は納付金制度で優遇される仕組みもあります。一般枠で採用した場合にはこうした特別な助成はありません。
専門の支援機関
障害者枠の場合、公的な支援機関や就労移行支援事業所、地域障害者職業センターなどが一貫してサポートを行うため、求人探しや面接対策、就職後の定着支援まで受けられます。ジョブコーチの派遣や就労定着支援など制度が充実しており、トラブルがあっても早期に相談しやすいです。一般就労ではこうした専門支援機関の利用が限定的になり、自分で転職エージェントやハローワークを利用して活動するのが基本になります。
給与面の違い
平均給与水準
障害者雇用(障害者枠)と一般枠では賃金に大きな差があります。身体障害者の場合はフルタイム採用されやすいため平均月収が比較的高めですが、知的障害や精神障害の場合はパート・アルバイト採用が多く、平均月収が低くなります。一般枠であれば正社員として採用されると基本給や賞与、昇給なども期待できますが、障害者枠では非正規で始まることが多いため年収に差が出やすいです。
昇給・賞与の有無
一般枠では年次昇給や賞与があるのが通常ですが、障害者枠の場合は雇用形態によって昇給や賞与がないことも珍しくありません。正社員登用されれば一般社員と同等に扱われる企業もありますが、補助的業務が中心だと大幅な昇給は見込みにくいのが現状です。
社会保障の違い
雇用形態が同じであれば、社会保険(健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険)の加入条件や内容に大きな差はありません。週の所定労働時間が30時間以上なら強制加入となり、20〜30時間でも要件を満たせば加入できます。障害者手帳所持者は失業給付の所定給付日数が健常者より長く、税制上の障害者控除が受けられるなど優遇措置があります。障害年金は就労の有無にかかわらず受給できるため、働きながら障害年金を併給することも可能です。こうした点で障害者雇用のほうがセーフティネットが手厚いと言えます。
キャリア移行の可否
障害者枠から一般枠への移行
障害者枠で入社後に一般雇用枠へ移行することは可能です。転職による移行はもちろん、同じ会社で障害者手帳を返納して「もう配慮は必要ない」と判断された場合、一般社員と同じ条件で働くケースもあります。ただし一般枠では配慮が減る分、体調管理などは自己責任になるため、自分の障害特性を十分コントロールできる必要があります。
一般枠から障害者枠への移行
逆に一般雇用で働いている途中で障害が判明し、手帳を取得した場合、会社の了承を得て障害者雇用枠へ切り替えるケースもあります。あるいは在職中に転職活動をして別の企業の障害者枠に応募する方法もあります。障害者枠に移行すると合理的配慮が受けやすくなる反面、雇用形態や待遇が変化する可能性もあるため、事前の相談が大切です。
比較表(一般就労 vs 障害者雇用の違い)
|
項目 |
一般就労(一般雇用枠) |
障害者雇用枠 |
|
対象者 |
応募条件を満たせば誰でも応募可能(障害の有無不問)。手帳取得は不要。 |
身体障害・知的障害・精神障害(発達障害を含む)などで手帳を所持している人が応募可能。入社時に手帳の提示が必要。 |
|
雇用形態・待遇 |
正社員・契約社員・パート等あらゆる形態がある。正社員比率は相対的に高く、昇給・賞与、福利厚生も充実していることが多い。 |
非正規雇用(契約社員・パート)の割合が高い。身体障害者は比較的正社員比率が高いが、知的・精神障害者は短時間勤務やアルバイト形態が多い。 |
|
採用プロセス |
ハローワーク一般求人や民間求人サイト、転職エージェントなど多様。 |
ハローワーク障害者窓口、障害者向け求人サイト、就労移行支援などを活用。 |
|
働き方(業務・勤務時間) |
職種・業務内容は幅広く、営業や企画、技術、管理部門など多岐にわたる。 |
個々の障害特性に合わせて職務を限定する場合が多い(事務補助、庶務、軽作業など)。 |
|
支援制度 |
公的助成金や専門支援は基本的になし。 |
国・自治体による助成金や奨励金が多数(特定求職者雇用開発助成金、トライアル雇用助成金など)。 |
|
給与水準 |
平均月収は正社員なら比較的高く、賞与や昇給も期待できる。 |
全体的に平均月収が低め。正社員登用されれば一般社員並みの待遇となる場合もあるが、短時間勤務やパート比率が高く年収面で差がつきやすい。 |
|
社会保障 |
雇用形態がフルタイムなら社会保険に加入。失業給付は通常の日数(自己都合退職の場合90~150日程度)。 |
社会保険の加入条件は基本的に一般就労と同じ。 |
|
キャリア移行 |
在職中に障害が判明して手帳取得した場合、会社の了承を得て障害者雇用枠へ切り替えることが可能。 |
就労経験を積んで障害の状態が安定すれば、手帳を返納して一般枠に移行する人もいる。 |



