- 抗うつ薬とは
- 抗うつ薬の服用期間
- 抗うつ薬の種類
- SSRI(選択的セロトニン再取り込み阻害薬)
- SNRI(セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害薬)
- NaSSA(ノルアドレナリン作動性・特異的セロトニン作動性抗うつ薬)
- 三環系抗うつ薬
- 四環系抗うつ薬
- その他
- 漢方薬
- 抗うつ薬の中止方法
抗うつ薬とは
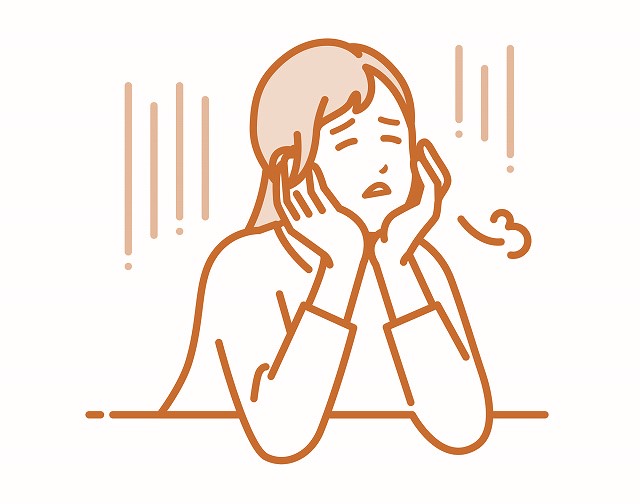 抗うつ薬は、うつ病やパニック障害、社交不安障害、強迫性障害、全般性不安障害、PTSD(心的外傷後ストレス障害)の治療に用いられる薬です。主に脳内の神経伝達物質の働きを調整することで効果を発揮します。
抗うつ薬は、うつ病やパニック障害、社交不安障害、強迫性障害、全般性不安障害、PTSD(心的外傷後ストレス障害)の治療に用いられる薬です。主に脳内の神経伝達物質の働きを調整することで効果を発揮します。
代表的な種類には、SSRI(選択的セロトニン再取り込み阻害薬)、SNRI(セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害薬)、NaSSA(ノルアドレナリン作動性・特異的セロトニン作動性抗うつ薬)があります。これらは新規抗うつ薬と呼ばれ、従来の三環系・四環系抗うつ薬に比べて副作用が少ないのが特徴です。
副作用としては、頭痛、消化器症状、不眠などが報告されています。まれに賦活症候群や不整脈などの重篤な副作用が起こることもあります。
効果の発現には通常2〜4週間程度かかります。再発予防のために、症状が改善してから半年~9か月継続することが多いです。医師の指示に従って適切に服用することが重要です。
抗うつ薬の服用期間
初期治療期
抗うつ薬の効果は、一般的に2〜4週間の服用で現れ始めます。ただし、個人差があり、効果の発現にはもう少し時間がかかる場合もあります。この期間中は、副作用の有無や症状の変化を注意深く観察し、必要に応じて薬剤の種類や用量の調整を行います。
維持療法期
症状が改善した後も、再発予防のために少なくとも6か月以上の継続服用が推奨されます。これは、脳内の神経伝達物質のバランスを安定させ、再発リスクを低減するためです。実際、早期に薬を中止すると再発率が高まることが、日本うつ病学会のガイドラインでも示されています。
長期療法
過去にうつ病を再発された方や、症状が重度であった場合は、1年以上の長期療法が必要となることもあります。最新の研究では、長期的な抗うつ薬の服用が再発予防に有効であることが報告されています(参考文献:厚生労働省 うつ病の治療)。
抗うつ薬の種類
抗うつ薬は主に以下の5種類に分類されます。
SSRI(選択的セロトニン再取り込み阻害薬)
セロトニン受容体に選択的に作用し、副作用が比較的少ないため広く使用されています。
具体的には、パキシル(パロキセチン)やジェイゾロフト(セルトラリン)、レクサプロ(エスシタロプラム)、デプロメール/ルボックス(フルボキサミン)があります。
SNRI(セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害薬)
セロトニンとノルアドレナリンの両方に作用し、特に意欲や活動性の低下に効果があります。
具体的には、サインバルタ(デュロキセチン)やイフェクサー(ベンラファキシン)、トレドミン(ミルナシプラン)があります。
NaSSA(ノルアドレナリン作動性・特異的セロトニン作動性抗うつ薬)
SSRIやSNRIとは異なる作用機序で、比較的短時間で効果があらわれると考えられています。
具体的には、リフレックス/レメロン(ミルタザピン)があります。
三環系抗うつ薬
古くから使用されている薬剤で、効果が強いですが副作用も多い傾向があります。
具体的には、アナフラニール(クロミプラミン)やトフラニール(イミプラミン)、トリプタノール(アミトリプチリン)、ノリトレン(ノリトリプチリン)があります。
四環系抗うつ薬
三環系抗うつ薬よりも副作用が少ないですが、効果はより緩やかとされています。
具体的には、テトラミド(ミアンセリン)やルジオミール(マプロチリン)、テシプール(セチプチリン)があります。
現在は、副作用が比較的少ないSSRI、SNRI、NaSSAを主に使用します。
SSRI
(選択的セロトニン再取り込み阻害薬)
パキシル(パロキセチン)
うつ病やうつ状態、パニック障害、強迫性障害、社交不安障害、PTSDなどの治療に用いられます。セロトニンを増加させる作用に特化しており、気分の落ち込みや不安の改善に効果があります。効果の発現が比較的早いのが特徴ですが、副作用にも注意が必要です。主な副作用には、嘔気や下痢などの胃腸症状、不眠、性機能障害があります。また、服用開始時の賦活症候群や、減量時の離脱症状にも注意が必要です。
ジェイゾロフト(セルトラリン)
ジェイゾロフトは、うつ病、パニック障害、強迫性障害、心的外傷後ストレス障害(PTSD)に対して処方する薬です。憂うつな気持ちや、不安やイライラ、やる気がなくなるなどの心の症状や、食欲がなくなる、眠れないなどの体の症状を改善します。恐怖心を和らげる作用もあります。脳内の神経伝達物質(セロトニン)の量を増やすことにより、憂うつな気持ちや落ち込んでいる気分を和らげる働きがあります。突然の動悸やめまいなどとともに強い不安があらわれるパニック発作や発作が起こることへの不安感を改善する薬です。副作用としては、傾眠、悪心、嘔吐、睡眠障害、不眠、錯乱状態、悪夢、易怒性(怒りっぽくなる)があります。用法は、1日1回口から服用します。
レクサプロ(エスシタロプラム)
レクサプロは、うつ病、パニック障害、強迫性障害、心的外傷後ストレス障害(PTSD)に対して処方する薬です。憂うつな気持ちや、不安やイライラ、やる気がなくなるなどの心の症状や、食欲がなくなる、眠れないなどの体の症状を改善します。人前での強い緊張や不安感、ふるえなどの症状を改善する効果もあります。脳内の神経伝達物質(セロトニン)の量を増やすことにより、憂うつな気持ちや落ち込んでいる気分を和らげる働きがあります。主な副作用としては、眠気、頭痛、倦怠感、浮動性めまい、悪心、口渇、異常感、無力症、浮腫、熱感、発熱があります。用法は、1日1回夕食後に口から服用します。
デプロメール/ルボックス(フルボキサミン)
うつ病やうつ状態、強迫性障害などの治療に用いられます。セロトニンの再取り込みを阻害することで、脳内のセロトニン濃度を上昇させ、抗うつ効果を発揮します。主な副作用には、悪心や眠気、口渇、便秘などがあります。また、性機能障害や離脱症状にも注意が必要です。24歳以下の方では自殺念慮のリスクが増加する可能性があるため、慎重に使用していきます。
SNRI
(セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害薬)
サインバルタ(デュロキセチン)
サインバルタは、うつ病に対して処方する薬です。憂うつな気持ちや、不安やイライラ、やる気がなくなるなどの心の症状や、食欲がなくなる、眠れないなどの体の症状を改善します。脳内の神経伝達物質(ノルアドレナリンやセロトニン)の量を増やすことにより、憂うつな気持ちや落ち込んでいる気分を和らげる働きがあります。また、中枢神経の痛みを抑える経路に働いて、痛みを和らげる働きがあります。そのため、糖尿病や線維筋痛症による痛み、腰や関節の痛みなどを和らげる薬としても使われています。副作用としては、悪心・嘔吐、下痢、倦怠感、眠気、頭痛、めまい、口渇、便秘、尿閉、CK上昇があります。用法は、1日1回朝食後に口から服用します。
イフェクサー(ベンラファキシン)
イフェクサーは、うつ病に対して処方する薬です。憂うつな気持ちや、不安やイライラ、やる気がなくなるなどの心の症状や、食欲がなくなる、眠れないなどの体の症状を改善するお薬です。脳内の神経伝達物質(ノルアドレナリンやセロトニン)の量を増やすことにより、憂うつな気持ちや落ち込んでいる気分を和らげる働きがあります。副作用としては、発汗、下痢、傾眠、浮動性めまい、頭痛、不眠症、悪心、腹部不快感、腹痛、腹部膨満、便秘があります。用法は、1日1回食後に口から服用します。
トレドミン(ミルナシプラン)
うつ病やうつ状態の治療に用いられます。セロトニンとノルアドレナリンの両方に作用し、特に意欲や活動性の低下に効果があります。他のSNRIと比較して離脱症状のリスクが低いとされています。主な副作用には、口渇や便秘、悪心、眠気などがあります。重大な副作用として悪性症候群やセロトニン症候群にも注意が必要です。高齢者では初期量を1日25mgとし、慎重に増量します。
NaSSA
(ノルアドレナリン作動性
・特異的セロトニン作動性
抗うつ薬)
リフレックス/レメロン(ミルタザピン)
リフレックスは、うつ病に対して処方する薬です。憂うつな気持ちや、不安やイライラ、やる気がなくなるなどの心の症状や、食欲がなくなる、眠れないなどの体の症状を改善するお薬です。脳内の神経伝達物質(ノルアドレナリンやセロトニン)の量を増やすことにより、憂うつな気持ちや落ち込んでいる気分を和らげる働きがあります。他の抗うつ薬と比べて睡眠や食欲への作用が強いため、不眠や食欲不振の症状が強い方に使うことが多いです。副作用としては、眠気、体重増加、倦怠感、浮動性めまい、頭痛、便秘、口渇、紅斑、肝障害があります。用法は、1日1回就寝前に口から服用します。
三環系抗うつ薬
アナフラニール(クロミプラミン)
主にうつ病・うつ状態、ナルコレプシーに伴う情動脱力発作の治療に用いられます。セロトニンとノルアドレナリンの再取り込みを阻害し、強い抗うつ効果を発揮します。特に強迫性障害に対する効果が高いことで知られています。副作用には、悪性症候群やセロトニン症候群、てんかん発作、横紋筋融解症などがあります。また、抗コリン作用による口渇や便秘、眠気などにも注意が必要です。MAO阻害剤との併用は禁忌とされています
トフラニール(イミプラミン)
主にうつ病・うつ状態、遺尿症の治療に用いられます。セロトニンとノルアドレナリンの再取り込みを阻害し、抑うつ気分や意欲低下の改善に効果がありま通常、成人の初期用量は1日30〜70mgで、最大200mgまで漸増します。主な副作用には、口渇、めまい、眠気、便秘などがあります。重大な副作用として、悪性症候群、セロトニン症候群、てんかん発作、無顆粒球症などに注意が必要です。MAO阻害剤との併用は禁忌です。
トリプタノール(アミトリプチリン)
主にうつ病・うつ状態、夜尿症、末梢性神経障害性疼痛の治療に用いられます。セロトニンとノルアドレナリンの再取り込みを阻害し、抑うつ気分や意欲低下の改善に効果があります。主な副作用には、眠気、口渇、悪心・嘔吐、便秘などがあります。重大な副作用として、悪性症候群、セロトニン症候群、心筋梗塞、幻覚、せん妄などに注意が必要です。服用中は、自動車の運転など危険を伴う機械の操作は避けてください。
ノリトレン(ノリトリプチリン)
主にうつ病やうつ状態の治療に用いられます。ノルアドレナリンへの作用が強く、意欲低下の改善に効果があります。また、治療抵抗性うつ病に対しても有効とされています。主な副作用には、口渇や眠気、便秘があります。重大な副作用として、てんかん発作、無顆粒球症、麻痺性イレウスなどに注意が必要です。自動車の運転など危険を伴う機械の操作は避けるようにしてください。
四環系抗うつ薬
テトラミド(ミアンセリン)
主にうつ病やうつ状態の治療に用いられますが、睡眠薬としても使用されます。シナプス前α2アドレナリン自己受容体を阻害し、ノルアドレナリンの放出を促進します。また、セロトニンに対して抗セロトニン作用を持ちます。主な副作用には、眠気、口渇、便秘、悪心・嘔吐などがあります。重大な副作用として、悪性症候群や無顆粒球症に注意が必要です。睡眠薬としての効果は、中途覚醒や早朝覚醒の改善に有効です。依存性や耐性のリスクが低いのが特徴ですが、翌日の眠気が残りやすいため、用量調整をしていきます。
ルジオミール(マプロチリン)
主にうつ病やうつ状態の治療に用いられます。ノルアドレナリンの再取り込みを強力に阻害し、意欲低下の改善に効果があります。三環系抗うつ薬のアミトリプチリンと比較して効果発現が早いとされています。主な副作用には、眠気、口渇、便秘、悪心などがあります。重大な副作用として、悪性症候群、てんかん発作、無顆粒球症などに注意が必要です。MAO阻害剤との併用は禁忌であり、心筋梗塞の回復初期や閉塞隅角緑内障の患者さんも使用できません。
テシプール(セチプチリン)
主にうつ病やうつ状態の治療に用いられます。三環系抗うつ薬に比べて副作用が軽く、作用の発現が速く、持続時間が長いとされています。主な副作用には、眠気、口渇、めまい・ふらつき、便秘などがあります。重大な副作用として、悪性症候群や無顆粒球症に注意が必要です。妊娠中の方は使用を注意する必要があります。
その他
デジレル/レスリン(トラゾドン)
デジレル/レスリンは、セロトニン5-HT2A、5-HT2C受容体阻害作用とセロトニン再取り込み阻害作用を持つ抗うつ薬です。抗うつ効果は100mg以上で得られるとされていますが、この用量では眠気が強く出現するため、現在は主に睡眠薬として使用されることが多いです。依存性や耐性のリスクが低く、他のSSRIで問題となる性機能障害のリスクも低いとされています。副作用には眠気、めまい、頭痛などがあります。また、QT延長や心室頻拍などの重大な副作用にも注意が必要です。
ドグマチール(スルピリド)
ドグマチールは、慢性胃炎、適応障害、躁うつ病(双極性障害)、統合失調症に対して処方される薬です。胃潰瘍や十二指腸潰瘍などの治療でも使われます。胃腸の血液の流れを増やし、粘膜を修復するとともに胃腸の運動をよくする働きがあります。強い不安や緊張感を和らげ、心の病気で起きる幻覚、妄想などを抑えます。不安や緊張などの精神の不安定な状態を抑える働きがあります。副作用としては、月経異常、乳汁分泌、女性化乳房、錐体外路症状(歩行障害、筋強剛、嚥下障害など)、肝障害、ジストニア、ジスキネジア、高プロラクチン血症、掻痒感があります。用法は、症状に応じて1日に2〜3回に分けて口から服用します。
ビプレッソ(クエチアピンフマル酸塩徐放錠)
ビプレッソは、躁うつ病(双極性障害)、統合失調症に対して処方される薬です。脳内の神経伝達物質の働きを良くして、憂うつで落ち込んだ気分、意欲や行動の低下している状態を改善します。気分が晴々しない憂うつな気持ちや不安を和らげる作用があります。脳内の神経伝達物質の働きを良くして、憂うつで落ち込んだ気分、意欲や行動の低下している状態を改善する働きがあります。副作用は、口渇、倦怠感、傾眠、便秘、めまい、頭痛、アカシジア、食欲亢進、高プロラクチン血症、口内乾燥、体重増加があります。用法は、1日1回就寝前とし、食後2時間以上あけて口から服用します。また、2日以上の間隔をあけて状態を観察しながら服用します。
トリンテリックス(ボルチオキセチン)
うつ病・うつ状態の治療に用いられる新しい抗うつ薬です。セロトニン再取り込み阻害作用とセロトニン受容体調節作用を持ちます。副作用が比較的マイルドで、1日1回の服用で効果が期待できます。また、離脱症状が少なく、性機能障害のリスクも低いとされています。通常、成人には1日10mgを経口投与し、最大20mgまで増量可能です。効果は2週間〜1か月程度で現れ始めます。主な副作用には悪心、傾眠、頭痛、めまいなどがあります。重大な副作用としてセロトニン症候群やけいれんに注意が必要です。
漢方薬
当クリニックでは、西洋薬だけでなく漢方薬を使用することもあります。
当クリニックでも処方される代表的な漢方薬について御説明します。詳しくは受診時に相談ください。
主に不眠・不安に対して使う漢方薬
酸棗仁湯(サンソウニントウ)
酸棗仁湯は、体力が低下し、心身が疲労している人の不眠改善に用いられる漢方薬です。特に覚醒と睡眠のリズムが乱れ、夜間目が冴えて眠れない、夢見が多い、熟睡感がないといった症状に適しています。主な構成生薬は酸棗仁、茯苓、川芎、知母、甘草です。これらが神経の高ぶりを鎮め、熟睡を促します。抑うつ、不安、焦燥感などの精神状態を伴うことが多い症状にも効果があります。副作用として、偽アルドステロン症やミオパチーに注意が必要です。これらは甘草による副作用で、血圧上昇や体重増加、手足のしびれなどの症状があらわれることがあります。
加味逍遙散(カミショウヨウサン)
加味逍遥散は、体力中等度以下で、のぼせ感があり、肩こり、疲れやすく、精神不安やいらだちなどの精神神経症状がある人に用いられる漢方薬です。更年期障害や月経不順、冷え症などの症状に効果があります。血行を促進してホルモンバランスの乱れを整え、精神を安定させる作用があります。主な副作用には、皮膚のかゆみ、発疹・発赤、吐き気・嘔吐、食欲不振などがあります。重大な副作用として、肝機能障害や黄疸にも注意が必要です
抑肝散(ヨクカンサン)
抑肝散は、イライラや不安、不眠などの精神神経症状を改善する漢方薬です。特に、怒りっぽく、カッとなりやすい人に適しています。認知症に伴う周辺症状(BPSD)の改善にも効果があるとされ、高齢者の不眠や不安にも用いられます。主な構成生薬は柴胡、釣藤鈎、川芎、茯苓、当帰、甘草、白朮です。副作用として、偽アルドステロン症やミオパチーに注意が必要です。
半夏厚朴湯(ハンゲコウボクトウ)
半夏厚朴湯は、不安や緊張による咽喉の違和感(のどのつまり感)や動悸、不眠などの症状に用いられる漢方薬です。ストレスによる自律神経の乱れを整え、精神的な緊張を和らげる効果があります。また、つわりや更年期障害にも用いられることがあります。主な構成生薬は半夏、厚朴、茯苓、蘇葉、生姜です。副作用として、まれに肝機能障害や間質性肺炎が報告されています。
便秘に対して使う漢方薬
麻子仁丸(マシニンガン)
麻子仁丸は、便秘に対して効果的な漢方薬です。特に、便が硬く排便が困難な状態に適しています。腸をうるおし、便を軟らかくする作用があり、無理なく体質に合った便秘改善が期待できます。主な構成生薬は麻子仁、大黄、枳実、厚朴などです。体力中等度以下で、便秘に伴う頭重、のぼせ、湿疹、にきびなどの症状にも効果があります。副作用として、下痢や腹痛に注意が必要です。また、他の下剤との併用は避けます。
大建中湯(ダイケンチュウトウ)
大建中湯は、腹部の冷えや動きの悪さによる便秘に効果的な漢方薬です。腸の働きを改善し、お腹の張りや痛みを和らげる作用があります。特に虚弱体質で腹部が冷えている人に適しています。機能性便秘のような腸の動きが悪くなった状態での症状改善が期待できます。副作用として、発疹、発赤、かゆみなどの皮膚症状があります。まれに間質性肺炎や肝機能障害が報告されているため、注意が必要です。
六君子湯(リックンシトウ)
六君子湯は、主に胃腸の働きを改善する漢方薬ですが、便秘にも効果があるとされています。食欲不振の改善や胃腸機能の向上を通じて、便秘症状を和らげる可能性があります。グレリンというホルモンの分泌を促進し、食欲を増進させる作用があります。また、腸の活動を促進し、スムーズな排便を助ける効果も期待できます。副作用として、発疹、蕁麻疹、下痢、悪心、腹部膨満感などがあります。
むくみ・肥満に対して使う漢方薬
防風通聖散(ボウフウツウショウサン)
防風通聖散は、体力があり、のぼせぎみで便秘がちな肥満症の人に用いられる漢方薬です。むくみや肥満の改善に効果があります。脂肪分解・燃焼促進、便秘解消、むくみ改善、食欲抑制などの作用があります。18種類の生薬で構成され、全身の代謝を高める効果があります。主な副作用には、発疹、胃部不快感、下痢などがあります。まれに肝機能障害や間質性肺炎の報告もあるため、注意が必要です。効果の発現には個人差がありますが、通常2週間から1か月程度で効果が現れ始めるとされています。
当帰芍薬散(トウキシャクヤクサン)
当帰芍薬散は、体力が低下し、冷えやむくみがある人、特に貧血傾向の強い女性に用いられる漢方薬です。水分代謝と血流を促進し、むくみを改善する効果があります。また、便秘改善や貧血傾向の改善にも効果があります。主な副作用には、胃部不快感、食欲不振、下痢などがあります。まれに肝機能障害の報告もあるため、注意が必要です。体重増加の副作用はないとされていますが、個人差があるため、使用中は定期的に体重をチェックすることが推奨されます。
補中益気湯(ホチュウエッキトウ)
補中益気湯は、体力が低下し、疲れやすく、食欲不振で、ときに微熱、寝汗、むくみなどを伴う人に用いられる漢方薬です。気虚(体力低下)の改善、食欲不振の改善、むくみの軽減などの効果があります。全身の機能を高めることで、結果的にむくみを軽減します。主な副作用には、胃部不快感、食欲不振、下痢などがあります。まれに間質性肺炎や肝機能障害の報告もあるため、注意が必要です。効果の発現には個人差がありますが、通常2〜4週間程度で効果が現れ始めるとされています。
五苓散(ゴレイサン)
五苓散は、体力中等度以上で、のどが渇して尿量が少ない人に用いられる漢方薬です。むくみの改善に効果があります。むくみの改善、利尿作用、暑気あたりの改善などの効果があります。水分代謝を改善し、むくみを解消します。主な副作用には、胃部不快感、下痢などがあります。まれに肝機能障害の報告もあるため、注意が必要です。夏バテや二日酔いにも効果があるとされていますが、過度の利尿作用による脱水に注意が必要です。十分な水分補給を心がけることが重要です。
抗うつ薬の中止方法
医師の指導のもとでの減薬
抗うつ薬の中止は、必ず医師の指導のもとで徐々に行う必要があります。自己判断での急な中止は、離脱症状(めまい、頭痛、不安感など)や症状の再発を引き起こす可能性があります。一般的には、数週間から数か月をかけて減薬します。
離脱症状への対応
減薬中に離脱症状が現れた場合は、すぐに医師にご相談ください。必要に応じて減薬スケジュールの調整や、一時的に用量を戻すことも検討します。
心理療法との併用
抗うつ薬による薬物療法と認知行動療法(CBT)などの心理療法を併用することで、治療効果が向上し、再発予防にもつながります。心理療法は、思考や行動のパターンを見直し、ストレスへの対処法を身につけるのに有効です。



